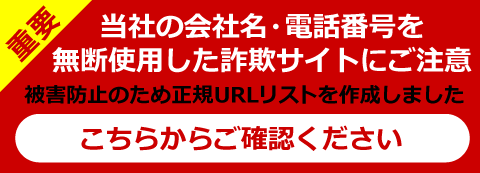
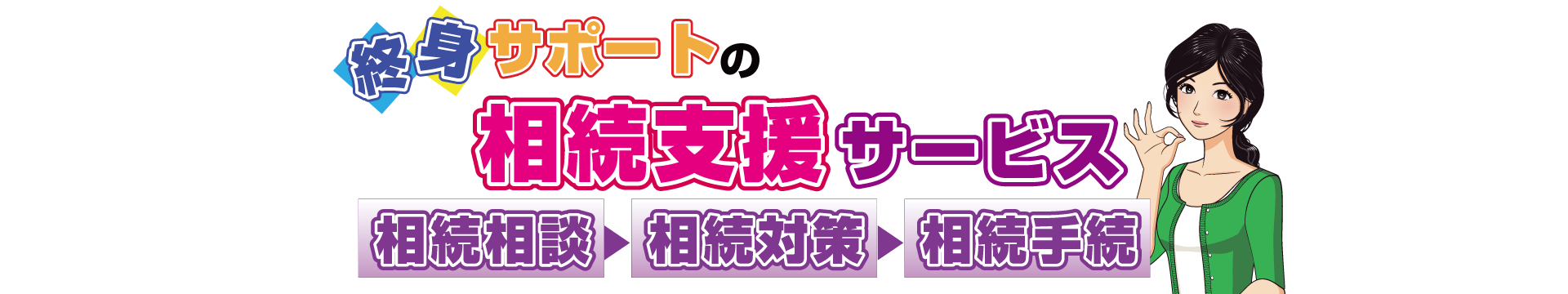
相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。相続人が被相続人から財産上の権利義務を承継することです。
相続支援サービスは、実に人間らしい世界です。だから士業さんの世界になってしまいますが……一般の人が相続に対して馴染みが薄すぎるのでは……この世界を理解すれば、そんなに難しいお話しではないようです。
ルールに従って対応すれば、収まるとこへと収まるのですが……実に人間らしいやり取り世界です!
相続は様々な法律の上で管理運営されていますので、相続をミスなく対処するためにも信頼できる相続に強い士業さんを活用することをおススメします。弊社(終楽)に相談頂きましたら、弊社(終楽)の相続に強い専門家集団の先生をご紹介いたします。
亡くなった人の財産のことです。<現金や預貯金>
遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。一方、遺言書がない場合はどうするのでしょう。民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。
また、相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。
未成年者が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。
相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。実際にどう確認するか。それは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認します。
先ずは、終楽にご相談ください。状況に応じた専門分野の先生をご紹介させ頂きます。※お気軽にご相談ください!
北海道・東北地方
関東地方

群馬県
公認会計士・税理士・経営コンサル
株式会社Rise
長瀬 大樹さん
対応エリア:首都圏

東京都
司法書士・行政書士
法務リンク司法書士法人
河合 星児さん
対応エリア:首都圏
中部地方

愛知県
弁護士 相続・離婚
鮫島 千遥さん

愛知県
公認会計士・税理士 相続・税務・会計
税理士法人エスペランサ
ふじた 美咲さん
関西地方

京都府
司法書士 財産管理・資産管理
司法書士事務所THE LEGAL
一般社団法人TLGライフエスコート
櫻井 博さん
対応エリア:全国
中国・四国地方
九州・沖縄地方
相続相談(お客様相続方針・希望)が優先か?相続対策・手続が優先か?
全体像(お客様の終身サポート最適化)がないのに相続対策・手続をすれば、士業さんペースでお話が進む。となると全体像とは何かとなります。お客様が望む終身サポート最適化です。終身サポート最適化とは?
相続対策の全体像とは?終活の相続対策とは?お客様が望む終身サポート最適化での相続対策となると、士業の先生方では現実的には対応しきれなくなります。
弊社(終楽)は相続対策・手続の専門家(スペシャリスト)ではありませんが、終身サポーターを多数擁しています。
終身サポート最適化相談は何でも屋(ジェネラリスト)の弊社(終楽)へ、相続対策・手続は専門家(スペシャリスト)の士業さんへとなります。弊社(終楽)は、弊社(終楽)の擁する専門家集団をご紹介させていただきます。
お気軽にご相談ください。士業さんのご紹介は無料で対応いたします!
原則的に生前に始末するモノです。弊社(終楽)は、被相続人様が元気なうちに対処することを強く強くおススメしています。
相続対策をするには、まず財産の把握・評価(被相続人様の財産)と相続人(親族)様の把握からはじまる。この2つを把握しないと相続対策は始まりません。
※第3版終身サポート最適化ノートをご覧ください。
家族が「争続」してしまう主な原因は、生前対策不足にあると思われます。相続は「準備が9割」と言われていますように、準備が非常に大切になります。遺産分割がスムーズにできるようにするために、5つのご提案をいたします。
Ⅰ.事前に被相続人様の考えをはっきりさせ、法定相続人様全員とのお話し合いをオススメします。(家族会議の生前開催)
Ⅱ.分割しやすい財産に組み替えます
Ⅲ.遺言書の作成
Ⅳ.生前贈与
Ⅴ.家族信託の活用
※課税価格は、110万円の基礎控除を差し引いた後の金額
※特別税率は直系尊属(父・祖父母)からの贈与による財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において20歳以下の者に限ります)について適用されます
相続税等がスムーズに支払えるようにします!
節税対策とは、支払う相続税をできるだけ少なくすること言います。具体的な対策は、
認知症を発症してから相続対策を行うと、相続に関する手続が行えなくなってしまう可能性があります。そのため、可能な限り認知症を発症する前の元気なうちに相続対策を行う必要があります。
※この相続業界は士業さんの世界ですので、日本中ほぼ同じかと思われます
財産をお持ちの方にとって、遺言は人生最大のイベントの一つだと思われます。
財産を法定に従って相続するのか、個人の意思によって寄付するのか???これを決めるのが、被相続人のお客様になります。
人生の流れの中で意識もせず何もせずに法定に従って、死後事務処理することも一つのやり方ですが……ある意図(遺言)で対応することを強くおススメします。
金額の大小でなく、お客様の生き様の最後の主張「アイデンティティ」だと思われます。終楽は、この手続きをご支援します。
当然、一般的な適正な対応もさせて頂きます。特に一族間の遺族争続を含めた小難しい対応もさせて頂きます。
お客様の財産の最終処分に関わることですので失敗が許されません。弊社(終楽)の専門家集団の士業さんを含めた対応とさせていただきます。
被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもの
※遺言(ゆいごん)と遺書(いしょ)の違い
被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をするもので、それを書面に残したものが遺言書です。
メディアから情報に「相続人不存在遺産768億円、約10年間で倍増」・「あなたのお金が社会を変える 広がる"寄贈寄付"」などがありました。一方で、「これって怪しい?遺贈寄付を装った詐欺に注意」などの情報も流れています。
お客様から遺贈についての終楽にご相談があった場合、今お住い又は故郷(ふるさと納税の延長で)の自治体さんをご紹介しています。
さてこの遺贈・死因贈与は使い勝手によっては、価値ある公的資産になるのでは!?!?遺贈する側から見れば、遺言者の意思で使い先を決められる!!!特に、お一人様の場合に、お役に立つ制度と思われます。
この件、生前に確りと使い道を検討されることをおススメします。終楽では力不足かもしれませんが、お客様の意に沿った対応をご提案させて頂きます。
遺留分とは、一定の相続人が最低限の相続財産を請求できる権利のことです。
たとえば、父親が遺言書で第三者に財産を渡すよう指定すれば、遺された配偶者や子どもたちの生活が立ち行かなくなる可能性があります。そこで、民法では配偶者や子どもに最低限の遺産相続を求める権利を認めています。 これが遺留分制度です。
遺言執行者とは、遺言を実現する役割を担う人を指します。公正証書遺言の件数増加や自筆証書遺言の制度変更により、遺言執行者に指定されるケースが増えています。
※一部対応できない地域があります、ご了承ください。
メディアからの情報に「相続人不存在遺産768億円、約10年間で倍増」・「あなたのお金が社会を変える 広がる"遺贈寄付"」などがありました。一方で、「これって怪しい?遺贈寄付を装った詐欺に注意」などの情報も流れています。
お客様から遺贈について終楽にご相談があった場合、様々なご提案をご案内しています。
さてこの遺贈・死因贈与は使い勝手によっては、価値ある公的資産になるのでは!?!?遺贈する側から見れば、遺言者の意思で使い先を決められる!!!特に、お一人様の場合に、お役に立つ制度と思われます。
この件、生前に確りと使い道を検討されることをおススメします。終楽では力不足かもしれませんが、お客様の意に沿った対応をご提案させて頂きます。
相続手続は被相続人様がお亡くなりになってから始まります。
相続手続開始は他界後(死後)ではなく、相続手続の準備を事前にどんどん進められては如何でしょうか。まずは、財産目録作成から始めることをおススメします。
是非、弊社の第3版終身サポート最適化ノートをご利用いただければ、納得いただけると思われます。こんなことで残されたご家族の負担も小さくなり、後々のトラブルも回避できると思われます。
※第3版終身サポート最適化ノート(1,280円)

※遺産分割の交渉不成立(遺産分割の話し合いがまとまらない)の場合
相続人とは、相続する権利がある方。相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合。法律では、相続人とその相続分について下記のように決められている。
配偶者と子(第一順位)が相続する場合

配偶者は1/2、子は残りの1/2を人数で等分
配偶者と親(第二順位)が相続する場合

配偶者は2/3、父母は残りの1/3を人数で等分
子の1人が既に死亡しその孫がいた場合

死亡した子の子(被相続人の孫)は相続人となる※2
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合

配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を人数で等分
※1 実子と養子の相続分は同じです。
※2 相続人になるはずだった子が死亡しても、更にその子がいる場合は、第一順位の相続権を引き継げます。(代襲相続)
※3 第三順位の相続権はその子(相続人のおい・めい)
下記のような場合、遺産分割が出来ないような状況になります。これをいい加減に進めてしまうと、後から相続手続が無効になってしまうこともあります。
事前に家庭裁判所にて代理人選任の申し立てを行うなど、申請や手続に時間がかかる場合もありますので、該当する相続人がいるかどうか早い段階で確認し、適法に手続を進める必要があります。
相続税とは、被相続人の死亡により、被相続人の親族(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金です。遺言書によって譲り受けた財産についても相続税が課税されます。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して行わわれなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかります。
被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。 なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
※一部対応できない地域があります、ご了承ください。
