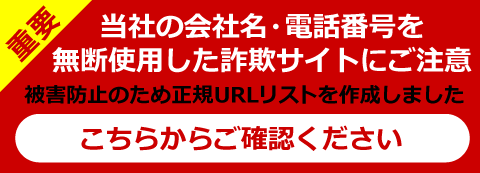
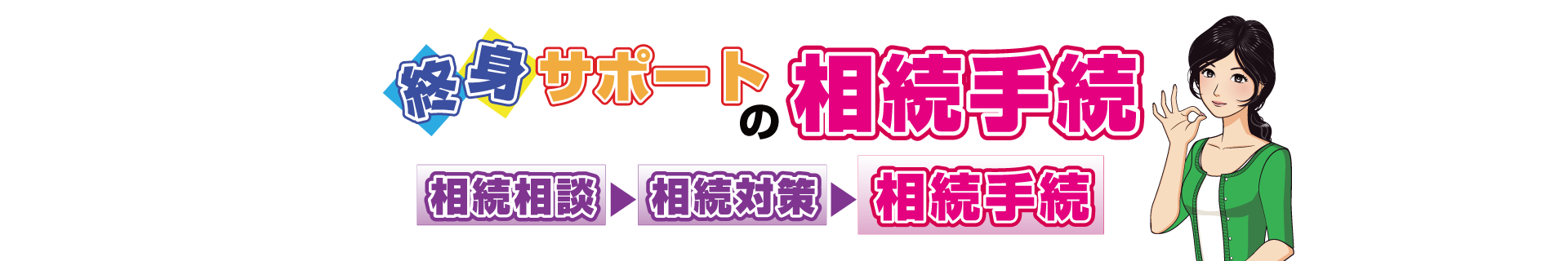
※第3版終身サポート最適化ノート(1,280円)

※遺産分割の交渉不成立(遺産分割の話し合いがまとまらない)の場合
相続人とは、相続する権利がある方。相続分とは、相続人が遺産を相続できる法律上の割合。法律では、相続人とその相続分について下記のように決められている。
配偶者と子(第一順位)が相続する場合

配偶者は1/2、子は残りの1/2を人数で等分
配偶者と親(第二順位)が相続する場合

配偶者は2/3、父母は残りの1/3を人数で等分
子の1人が既に死亡しその孫がいた場合

死亡した子の子(被相続人の孫)は相続人となる※2
配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続する場合

配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を人数で等分
※1 実子と養子の相続分は同じです。
※2 相続人になるはずだった子が死亡しても、更にその子がいる場合は、第一順位の相続権を引き継げます。(代襲相続)
※3 第三順位の相続権はその子(相続人のおい・めい)
下記のような場合、遺産分割が出来ないような状況になります。これをいい加減に進めてしまうと、後から相続手続が無効になってしまうこともあります。
事前に家庭裁判所にて代理人選任の申し立てを行うなど、申請や手続に時間がかかる場合もありますので、該当する相続人がいるかどうか早い段階で確認し、適法に手続を進める必要があります。
相続方法には「単純承認(単純相続)」「相続放棄」「限定承認」の3つの種類があります。
※遺産分割交渉が決裂の場合
遺産分割交渉が不成立の場合、弁護士さんにお願いすることになります。
6~12か月を目処に調停成立・審判へお話が進み、遺産分割が完了いたします。必要でしたら、弊社(終楽)のコラボ先弁護士さんをご紹介させて頂きます。
※名義変更手続が大変のようでしたら、弊社(終楽)のコラボ先士業さんをご紹介させて頂きます。
相続税とは、被相続人の死亡により、被相続人の親族(相続人)が相続で取得する財産に対して課税される税金です。遺言書によって譲り受けた財産についても相続税が課税されます。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して行わわれなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税・延滞税がかかります。
被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。 なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
※一部対応できない地域があります、ご了承ください。

相続手続は被相続人様がお亡くなりになってから始まります。
相続手続開始は他界後(死後)ではなく、相続手続の準備を事前にどんどん進められては如何でしょうか。まずは、財産目録作成から始めることをおススメします。
是非、弊社の第3版終身サポート最適化ノートをご利用いただければ、納得いただけると思われます。こんなことで残されたご家族の負担も小さくなり、後々のトラブルも回避できると思われます。